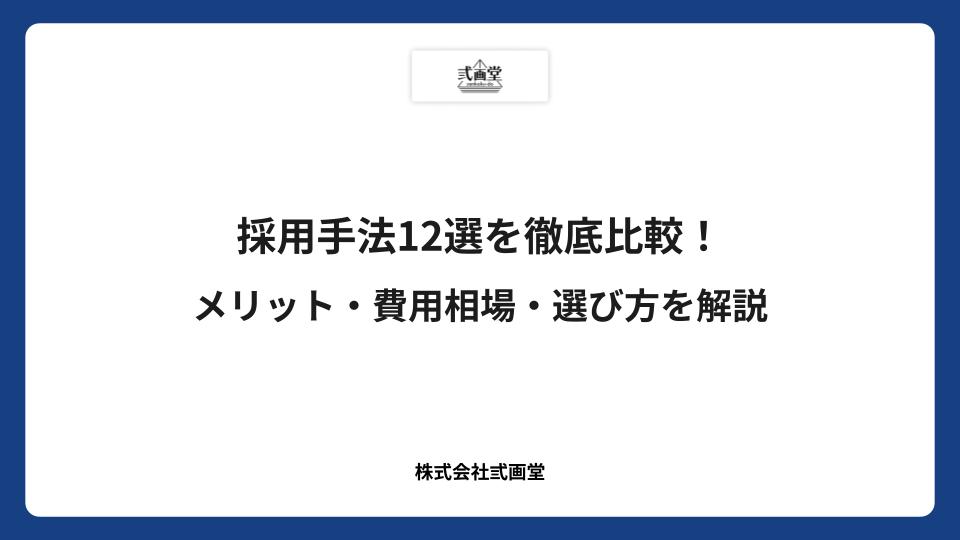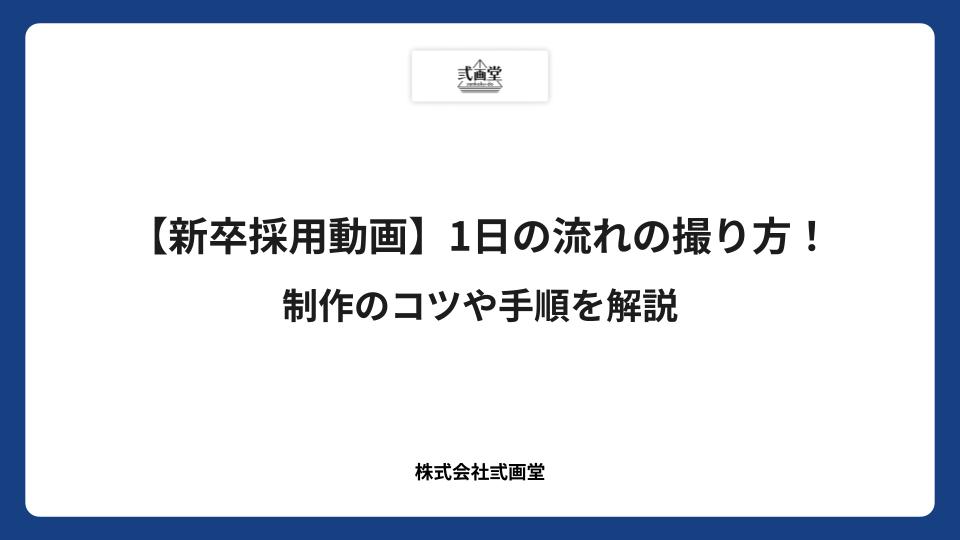記事公開日
最終更新日
採用課題とは何か?中小企業が陥る11の罠と解決方法
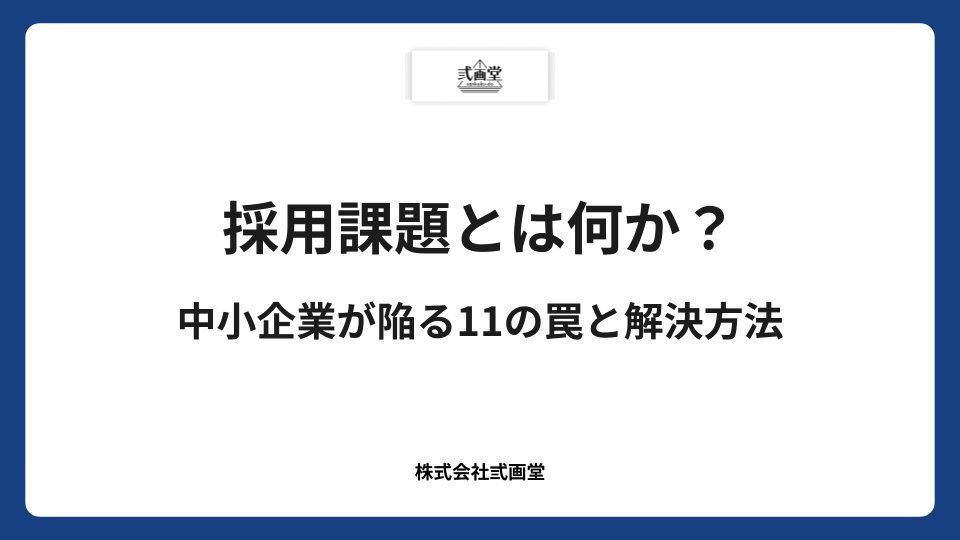
「良い人材がなかなか集まらない…」
「コストをかけているのに、採用がうまくいかない…」
「ようやく内定を出せても、辞退されてしまう…」
もし、あなたが経営者としてこのような採用の課題に頭を悩ませているなら、その原因は個別の施策にあるのではなく、もっと根深い「構造的な問題」にあるのかもしれません。実は、多くの中小企業が知らず知らずのうちに、採用活動における“負のスパイラル”に陥っています。
本記事では採用課題に関して、多くの中小企業が見落としている「11の罠」を具体的に解説します。
この記事を読み終える頃には、漠然としていた自社の採用課題が明確になり、「次に何をすべきか」という具体的な打ち手が見えてくるはずです。
「採用課題」とは何か?
多くの経営者が「採用がうまくいかない」と口にしていますが、その「課題」の正体を正確に捉えられているケースは多くありません。まずは、採用課題の本質について考えていきましょう。
採用課題とは、採用目標の達成を阻む「ボトルネック」のこと
採用課題とは、単なる悩みや問題点ではありません。「事業計画に基づいた採用目標の達成を、阻害している根本的な要因(ボトルネック)」と定義できます。
例えば、「新規事業を立ち上げるために、来期中にWebマーケターを2名採用する」という目標があったとします。この目標に対し、「そもそもWebマーケターからの応募が来ない」「応募は来るが、求めるスキルに満たない」といった事象が発生している場合、それがボトルネックであり、解決すべき採用課題となります。
漠然とした悩みを、具体的な「目標達成を阻むボトルネック」として捉え直すことが、課題解決のスタートラインです。
多くの経営者が見落とす「経営課題」と「採用課題」の繋がり
「採用は人事の仕事」と考えてはいないでしょうか。これは中小企業の採用における、非常によくある誤解です。採用課題は、常に経営課題と直結しています。
- 売上目標が未達 → 解決策:営業人員の増強(採用課題)
- 新サービスが開発できない → 解決策:特定のスキルを持つエンジニアの確保(採用課題)
- 次世代の幹部が育たない → 解決策:マネジメントポテンシャルのある若手の採用(採用課題)
このように、会社の未来を描く上で、人材の確保は避けて通れない問題です。採用の成功なくして、企業の持続的な成長はあり得ません。
なぜ今、多くの企業にとって採用が課題となっているのか?
近年、採用の難易度がかつてなく高まっています。その背景には、無視できない2つの外部環境の変化があります。
- 労働人口の減少と有効求人倍率の高止まりで日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少の一途をたどっています。人材の絶対数が減っているため、企業間の人材獲得競争は激化。2024年時点でも有効求人倍率は高い水準で推移しており、企業が求職者を選ぶ時代から、求職者が企業を選ぶ時代へと完全にシフトしています。
- 働き方の多様化と価値観の変化。終身雇用が当たり前ではなくなり、リモートワーク、副業、フリーランスなど、働き方は多様化しました。特に優秀な人材ほど、給与や待遇だけでなく、「やりがい」「成長環境」「企業のビジョンへの共感」「柔軟な働き方」といった要素を重視する傾向にあります。旧来の画一的な雇用条件だけでは、彼らの心に響かせることは困難です。
これらの環境下で、旧態依然とした採用活動を続けていては、人材獲得競争で勝ち抜くことはできません。
【自己診断】あなたの会社は大丈夫?企業が陥る「11の採用課題の罠」
ここでは、多くの中小企業が陥りがちな採用課題を「11の罠」として、採用プロセスに沿って解説します。自社がどの罠にはまっているか、診断してみてください。
【計画フェーズの罠】
採用活動の成否は、この計画フェーズで8割決まると言っても過言ではありません。
罠1:求める人物像が「優秀な人」と曖昧
経営者に「どんな人が欲しいですか?」と尋ねると、「とにかく優秀な人」という答えが返ってくることがあります。しかし、「優秀」の定義は会社やポジションによって全く異なります。定義が曖昧なままでは、誰に、何を、どうアピールすれば良いのかが定まらず、採用活動全体がブレてしまいます。
罠2:採用計画が場当たり的
欠員が出たら補充する、という場当たり的な採用になっていませんか?事業計画と連動した戦略的な採用計画がなければ、常に後手に回り、採用にかけられる時間も予算も限られてしまいます。結果として、妥協した採用に繋がりがちです。
罠3:自社の本当の魅力(強み)を言語化できていない
「うちは給料も高くないし、福利厚生も大手には敵わない…」と、自社の魅力を伝えることを諦めていませんか?知名度や待遇面で劣る中小企業だからこそ、「事業の独自性」「経営者との距離の近さ」「裁量権の大きさ」「特定の技術力」といった、他社にはない独自の魅力を明確に言語化し、伝える努力が不可欠です。
【母集団形成フェーズの罠】
計画が固まったら、次はいかにして候補者を集めるか、というフェーズです。
罠4:応募が全く集まらない
求人広告を出しても、全く応募がない。これは中小企業にとって最も深刻な課題の一つです。原因は、求人の魅力が伝わっていない、ターゲットに求人情報が届いていない、そもそも市場にターゲットが少ない、など複合的に考えられます。
罠5:ターゲットではない層からの応募ばかりで疲弊する
応募は来るものの、求めるスキルや経験とはかけ離れた候補者ばかり、というケースも多いのではないでしょうか?書類選考や面接に無駄な工数がかかると、採用担当者は疲弊してしまいます。これは、求める人物像が求人票に正しく反映されていないか、発信する媒体がターゲットとずれていることが原因の可能性が高いです。
罠6:大手と同じ求人媒体で“埋没”している
多くの企業が利用する大手求人ナビサイトは、知名度と掲載量で勝る大企業が有利なプラットフォームです。同じ土俵で戦おうとすると、多額の広告費をかけてもその他大勢の中に埋没し、候補者の目に留まることすら難しくなります。
【選考フェーズの罠】
応募者との貴重な接点である選考プロセスにも、多くの罠が潜んでいます。
罠7:面接官によって評価基準がバラバラ
社長の評価は高いが、現場マネージャーの評価は低い。このような事態は、評価基準が事前にすり合わされていないために起こります。面接官の主観や相性だけで合否が判断され、本来採用すべき人材を逃すリスクがあります。
罠8:「選んでやっている」という意識で、候補者の心を離している
面接官の態度が高圧的だったり、候補者の話を真摯に聞かなかったりするケースです。候補者はシビアに企業を見ています。選考は、企業が候補者を見極める場であると同時に、候補者が企業を見極める場でもあります。ここで悪い印象を与えれば、SNSなどで悪評が拡散するリスクすらあります。
罠9:選考プロセスが長く、機会損失を招いている
書類選考の結果連絡に1週間以上かかったり、面接回数が不必要に多かったりすると、優秀な候補者ほど他社の選考が先に進み、辞退されてしまいます。スピード感の欠如は、採用市場において致命的な機会損失に繋がります。
【内定後・入社後の罠】
採用は、内定を出して終わりではありません。
罠10:内定辞退が多発し、採用活動が振り出しに戻る
時間とコストをかけてようやく内定を出したにもかかわらず、辞退されてしまう。これは経営者にとって精神的なダメージも大きい問題です。内定から承諾までの期間に候補者の入社意欲を高める「内定者フォロー」が不足していることが主な原因です。
罠11:入社後のミスマッチで早期離職が起きる
採用した人材が、数ヶ月で辞めてしまう。これは採用コストが無駄になるだけでなく、既存社員の士気にも悪影響を及ぼします。選考段階で、企業のリアルな情報(良い面も厳しい面も)を伝えきれておらず、入社後の「こんなはずじゃなかった」というギャップを生んでいることが原因です。
なぜ、採用課題の罠に陥ってしまうのか?
11の罠を見て、いくつか自社に当てはまるものがあったかもしれません。では、なぜ多くの中小企業はこれらの罠に陥ってしまうのでしょうか。 個別の原因は様々ですが、それらを貫く根本原因が一つだけあります。
原因は「採用をマーケティング活動として捉えられていない」こと
これまでの日本の採用は、求人を出して応募者を「待つ」というスタイルが主流でした。しかし、売り手市場が常態化した今、その考え方は通用しません。
採用活動とは、「自社の魅力を、求める人材に正しく届け、ファンになってもらい、選んでもらうための一連の活動」です。これはまさしく、製品やサービスを顧客に届ける「マーケティング活動」そのものです。この発想の転換ができていないことが、あらゆる採用課題の根源にあるのです。
会社の魅力を「製品」、候補者を「顧客」と捉え直す思考法
採用をマーケティングとして捉え直してみましょう。
- 自社 → 魅力的な製品・サービス
- 候補者 → ターゲットとすべき顧客
- 求人媒体 → 広告チャネル
- 選考 → 営業・商談
- 入社 → 契約成立
このように置き換えると、やるべきことが明確になります。「どんな顧客(候補者)に」「自社という製品(会社)のどんな価値を」「どのチャネル(媒体)で」「どのように伝えて(選考)」契約してもらうか。この一連のプロセスを戦略的に設計するのが「採用マーケティング」です。
採用課題を解決し、欲しい人材を獲得するための4つのステップ
では、具体的に採用マーケティングをどのように進めればよいのでしょうか。ここでは、明日から考え始められる4つのステップをご紹介します。
STEP1:【現状分析】 自社の「採用の健康診断」を行う
まずは自社と市場を客観的に分析し、現在地を正確に把握します。マーケティングのフレームワークである「3C分析」を用いると効果的です。
- Company(自社分析):自社の本当の強み・弱みは何か?(事業内容、企業文化、働きがい、成長機会など)
- Competitor(競合分析):人材を取り合っている競合他社はどこか?その企業はどんな魅力を打ち出しているか?
- Customer(顧客=候補者分析):求める人材は、仕事や会社に何を求めているのか?どんな情報をどこから得ているのか?
STEP2:【戦略設計】 候補者の心に響く「採用コンセプト」を定める
現状分析ができたら、採用活動の軸となるコンセプトを定めます。「誰に、何を、どのように約束するか」を明確にするのです。
- 採用ペルソナの設定:罠1で触れた「求める人物像」を、スキルや経験だけでなく、価値観や志向性まで含めて具体的に描きます。
- EVP(従業員価値提案)の策定:分析した自社の魅力を基に、「この会社で働けば、こんな価値や経験が得られます」という、候補者への約束(EVP: Employee Value Proposition)を策定します。これが求人票や面接で語るべきメッセージの核となります。
STEP3:【チャネル選定】 自社に合った「出会いの場」を見つける
大手求人ナビだけに頼る必要はありません。設定したペルソナがどこにいるのかを考え、最適なチャネルを組み合わせます。
- ダイレクトリクルーティング:企業側から候補者に直接アプローチする「攻め」の手法。
- リファラル採用:社員の紹介による採用。ミスマッチが少なく定着率が高い傾向にあります。
- SNS採用:Instagram、FacebookやX(旧Twitter)などを活用し、企業のカルチャーや日常を発信してファンを増やします。
- 人材紹介:成功報酬型が多く、特定のスキルを持つ人材を狙う場合に有効です。
STEP4:【選考体験の向上】 ファンを作る「選考プロセス」を設計する
選考は、候補者の入社意欲を最大化するための重要なコミュニケーションの場です。候補者体験(Candidate Experience)の向上を意識しましょう。
- 連絡の迅速化・透明化:選考結果の連絡は可能な限り早く行い、次のステップを明確に伝えます。
- 面接官トレーニングの実施:評価基準の統一と、候補者の魅力を引き出す質問の仕方をトレーニングします。
- 魅力付けの場を作る:面接だけでなく、現場社員との座談会などを設け、会社のリアルな雰囲気を伝えます。
採用課題の解決は、会社の未来を変える第一歩
採用活動の変革は、一朝一夕にはいきません。しかし、その努力は必ず会社の未来を明るく照らします。
採用は「コスト」ではなく、最高の「未来への投資」
採用にかかる費用を、単なる「コスト」として見ていませんか?優秀な人材が一人入社することで、新しい事業が生まれたり、チーム全体の生産性が向上したりと、その投資額を何倍にも上回るリターンが期待できます。採用は、会社の未来を作るための最も重要な「投資」なのです。
強い組織作りのために、今すぐやるべきこと
ここまでお読みいただいた中で、様々な採用の課題とその解決の方向性が見えてきたのではないでしょうか。
強い組織作りのために、今すぐやるべきことは、「まず、自社の採用課題が11の罠のうちどこにあるのかを特定し、なぜそうなっているのかを深く考えること」です。そして、その課題解決を、最重要の経営マターとして位置づけることです。
自社の採用課題の特定・解決にお悩みなら
株式会社弎画堂は「採用マーケティング」で貴社を伴走支援します
「自社の課題は分かったが、具体的にどう解決すればいいか分からない」
「採用戦略を立てるための客観的な視点や人手が足りない」
もしそうお考えでしたら、ぜひ私たち株式会社弎画堂にご相談ください。私たちは、採用活動をマーケティングとして捉え、戦略立案から実行までを一気通貫で支援するプロフェッショナル集団です。
まずは無料の「採用戦略 壁打ち相談」で課題を整理しませんか?
貴社の現状や課題について、まずは私たちに話してみませんか?専門のコンサルタントが、客観的な視点で課題を整理し、解決の方向性を見出すお手伝いをいたします。下記ページより、お気軽にお問い合わせください。
株式会社弎画堂のサービスページはこちら
https://service.sankaku-do.co.jp/
【この記事の監修】
株式会社弎画堂
ムービーディレクター / フォトグラファー
相澤里志 Satoshi Aizawa